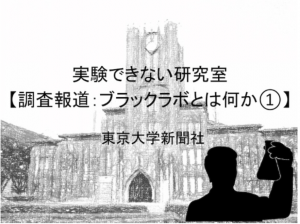M. Kuno
久野 美菜子
答えのない物語を面白いと思えるようになったのは、一体いつのことだったろう?
先月「戦場のメリークリスマス」で助監督を務めたロジャー・パルバースが来日した際、次のような言葉を述べていた。
「映画には何も答えはない。ただ、同じ状況になったらどうするか、一人一人考えてもらう。権力を持っている人が見てほしい視点とは、別の見方を提供するのも芸術の役割と思う」と。
いつの間にか予定調和な童話に物足りなくなり、漫画の中でジレンマに陥る若い少年に自身を重ね、途方にくれることで子供時代に別れを告げたように思う。しかし大人になった今とて、答えのない問題に対して善処するのは難しい。特に自分の生活や将来がかかった問題に対してはすぐにだって正解が欲しいものだ。
そんな時にふと思い出されるのは、大学に入りたての頃、とある授業で聞いた「学問において重要なことは答えを出すことではなく、適切な問を立てることだ」という、ごくベーシックでかつ示唆に富んだ警句である。
アメリカの物理学者アルビン・ワインバーグは「科学に問うことはできるけれども、科学が答えられない問題」を「トランスサイエンス」と呼んだ。たとえば原発の安全装置がすべて同時に故障すれば深刻な事態になることについて専門家の意見は一致する。しかし、その確率の低さと、安全装置の追加の是非については専門家の意見は分かれる。
「科学だけでは答えられない」からだ。複雑で様々な利害関係者が絡む問題においては、正解を見つけ出すのはほぼ不可能といえよう。そこで科学に求められるのは、一面的な解決策を提示することではなく、いまの世界に対して異なる視点を提示し、複数の未来を描くことで問題提起を行うことではないだろうか。
一方、非専門家である一般市民もそこで描かれた未来や立てられた問に対し、ともに考え更に問を深める必要がある。そうした際に重要なのは、華々しいノーベル賞の発表を単なる秋の風物詩として眺めるだけではなく、そもそも研究とはどのようなものか、科学者の営みや行動様式を知ることだろう。科学者と一般市民の双方が歩み寄る必要があるのだ。
21世紀において、科学の可能性のみならず、限界を感じる問題も噴出している。本稿では、筆者が運営する「研究の未来をデザインするメディア Lab−On(ラボオン https://lab-on.jp)」というwebメディアを紹介しつつ、私たちは科学をどう伝え科学とどう向き合っていくかについて考えたいと思う。
桶川ストーカー殺人事件と調査報道
小さい頃から理科や算数が得意で、科学雑誌をパラパラめくるのが好きだった。食品系の研究職に付きたくて農学部に進学し、味覚の研究をしていたのだが、ひょんなことからメディアに興味を持ち、メディアの可能性と面白さにずぶずぶはまった結果、農学部の院をやめてしまった。その後メディアやジャーナリズムの勉強が出来る院に入り直したのだが、文系科目が大の苦手だった私が文系の院に入り直し曲がりなりにも文章に携わる仕事をするようになるのだから人生わからない。
ジャーナリズムと一口にいっても様々な定義があり、それが指し示す範囲はとても広いので、ここでは私がジャーナリズムにはまるきっかけとなった調査報道と呼ばれる報道手法を紹介しよう。
調査報道というのは、政府や企業の発表に依存せず、記者自身の問題意識に沿って、独自の調査で丹念に事実を集める報道スタイルだ。
調査報道に興味を持ったのは、清水潔氏による桶川ストーカー殺人事件( 注1)について書いた本「桶川ストーカー殺人事件―遺言 (新潮文庫)」を読んだことがきっかけだ。著者である清水氏が、写真週刊誌『FOCUS』の記者だったころ、桶川で起こった女子大生殺人事件を独自に調査し、警察より先に自ら犯人グループを特定した。さらに捜査本部の置かれた埼玉県警上尾警察署の不正・怠慢が発覚したというもので、この事件がキッカケでストーカー規制法が出来たのである。
この記者がいなければ闇に葬られていたであろう事件の真相が調査報道によって明らかになり、さらに法律も整備された。
誰かが発信しなければ闇に埋もれてしまうようなことや、無視されてしまうことを俎上に載せる、言わば問を立てる行為であり、ジャーナリズムの核ともいえよう。しかし時間も人員もかかり訴訟のリスクもある調査報道は営利のメディアでは積極的に出来ないという現状もある。そうした問題を克服すべく非営利機関が調査報道を担う事例がここ数年、欧米中心に散見されるようになった。
調査報道の面白さに目覚めたと同時に今後のメディアのゆくえが気になった私は、大学院での研究テーマを「非営利メディアによる調査報道の可能性(注2)」に決めた。大学院にも少しずつ慣れ、図書館で事例の文献調査を進めていたある日のことだ。理系の研究とは違い、目に見えた進捗が出にくい研究スタイルに行き詰まりを感じていた私の頭に、ふとあるアイディアが降りてきた。
大学内でも調査報道が出来ないだろうかー?
マスメディアでは拾えない大学内の課題を、学生の手で発信できないだろうかー?
幸か不幸か、ミイラ取りがミイラになる一歩を踏み出してしまったのである。
タコつぼ研究室「ブラックラボ」
このアイディアを実現すべく、私は所属する東京大学新聞社で調査報道をすることにした。 調査対象は、かねてから気になっていたブラックラボ(研究室)問題だ(注3)。理系の学生の間では、ハラスメントが横行したり、長時間研究室にいることを強制したり、といった研究室を「ブラックラボ」と呼ぶ。
実際、私の周りにも研究環境が合わず大学をやめた友人や、軽い鬱の症状が出た友人がおり胸を痛めていたのだが、何をもって「ブラック」とするかは一概に言えず、個人の主観を排すこともできない。そのため「ブラックラボ」という言葉の存在自体が、学生の甘えの発露であるとも批判される。
たとえば、研究時間が長いところをブラックラボと決めつけるのは短絡的だ。時間を忘れるほど実験に熱中できる研究室は、研究が好きな者にとって最高の環境だろう。一方コアタイムがないと銘打っているにも関わらず、上の人が帰るまでは帰れない空気のある研究室は、名目上は自由な研究環境としながらも教授や助教の顔色を伺いながら研究をしなければならない。
また、指導の頻度や時間についてもブラックさと単純には結びつかない。先生の熱心すぎる指導により、条件検討や溶液調整と言った予備実験を繰り返すことを余儀なくされ、毎晩遅くまで続く議論で肝心の本実験をさせてもらえない研究室もあれば、普段は学生の研究は全く見ず、指導をしない一方で、発表時になって研究内容をとことん否定されるところもある。言葉の暴力や過度なプレッシャー、就活への妨害もあれば、学生のやる気のなさや不真面目な研究態度、打たれ弱さが問題視されることもある。
ブラックラボは学生の甘えなのか、それとも顕在化していない問題がひそんでいるのか?研究環境をよりよいものにするにはどうすればいいのか?その答えを探るべく、昨年の9月から理系の学生を中心に研究における悩みに関するヒアリングを重ね、研究室におけるブラックさとは何か考察した。
その結果、気づいたことがいくつかある。
まず第一に、ブラックラボはそのラボの主宰者である教授や准教授など、いわゆるPI(Principal Investigator, 研究室の運営を行う人)が、一概に悪いわけではないということ。もちろん、教授という強大な権力を利用したハラスメントは非難されてしかるべきだが、学生に十分に指導が出来ない研究室のリアルは、研究以外の雑務や研究費の獲得に疲弊している現状がある。
第二に、ブラックラボ問題以外にも、大学や研究機関が抱える課題がたくさんあるということ。研究上の不正行為、安定的な雇用の少なさ、研究資金の不足。運営交付金は2004年以降の法人化以降1%ずつ減らされており、競争的資金の割合が増しているいま、成果がすぐには出ない基礎研究に対する風当たりは強い。しかし物理的にも社会的にも閉じがちな研究環境は、その課題が明るみにでることは少ない。
「悪の葉っぱに斧を向ける者は千人いても、根っこに斧を向ける者は一人しかいない。」ヘンリー・デイヴィッド・ソローの言葉だ。
研究にまつわる課題の根っこには、一体何があるのだろうか?
記事に対しては、当初思っていた以上の反響があった。たくさんの人に読んでもらえたことも嬉しかったが、同じような状況で悩む学生からのメッセージや、先生方からのコメントで、少しでも誰かの力になっていることがわかり何よりの励みになった。自分が知らない遠くの誰かにも届くのだということに、高揚し、メディアの可能性を感じたと同時に、淡々と発信することの地道さに歯がゆい思いもしていた。
大学院で文系に転じて一番驚いたのは、部屋としての研究室がないことだった。理系の研究室のようにラボのメンバーが同じ空間で過ごすことはあまりない。せいぜい週に1度のゼミや研究会で顔を合わす程度だ。理系と文系の研究生活やスタイルに大きな差があり、知ろうとしない限り内実はわからない。同じ大学内ですら隔たりがあるのだから、学外の人との溝は決して浅いものではないだろう。
研究室の門戸を開放しよう
溝をいかに埋めるか、ということに悶々としていた頃に出会ったのが、いま私が働いている株式会社POL(ポル)の代表取締役CEOの加茂倫明氏だった。POLは研究者や理系学生向けのサービスを提供する会社だ。現在はLabBaseという理系学生と企業をマッチングするサービスをメインに提供しており、今後は研究環境の課題を解決するサービスを次々にリリースすることで日本にはまだない“LabTech産業(ラボテック)”を創出することを目指している。
加茂が私の書いた記事をシェアしてくれた事がきっかけで話をした。「研究環境をよりよくすることで科学の発展に寄与したい、内部に閉じがちなアカデミアをオープンにして、外部との関わりも促進したい」との思いが合わさった結果意気投合し、初めて会ったその日にwebメディアを立ち上げることになった。まだ出来て半年に満たない小さな会社だったが、広い海に乗り出すような胸の高鳴りを感じた。
そんなこんなで、加茂と出会って3ヶ月後にオープンさせたのが「研究の未来をデザインするメディア『Lab-On』」だ。”Make academia open & cool.”をコンセプトに、最先端の研究や研究者がどのような思いで研究に取り組んでいるかを伝えることで内部に閉じてしまいがちなアカデミアを社会に開き、研究者がもっと誇りを持って研究できる環境を作りたいとの思いで運営している。
コンセプトに示したオープンという言葉は複数のレイヤーで使っているのだが、大きく3つの意味がある。
まず第一に、アカデミアを社会に対してより開くということだ。というと「いやいや、万人に対して開かれているではないか」と反論されそうだが、たとえば教会をイメージするとわかりやすいだろう。アカデミアも教会も、どちらも一般に広く門戸を開いているが、そこに所属しない者にとっては得体の知れない世界だ。その世界の日々の営みや文化、しきたりがわからなければパブリックとしての機能は十分に果たせない。科学が福音ではなくなった今、プレスリリース的に科学の成果を世に伝えるだけでなく、研究者の営みを広く知らしめることで、研究者という生き方が特別なものではないということがわかるといいなと思う。
また、そうした隔たりは、アカデミアの中にだって存在する。研究は特定の分野を狭く深く掘り下げるため、専門知識は深いけれども他の研究分野に対する視野が狭くなりがちだ。このような状況を揶揄して、研究室はタコツボと称されることが多い。オープンイノベーションが声高に叫ばれる時代においては、「自分の専門領域を対象とした研究を頑張ればよい」ほど、世間は甘くない。研究者同士のSNSや研究費のクラウドファンディングが充実してきた今こそ、研究分野の境界を越えミッションドリブンで集まることで、より優れた研究成果をあげることができるのではないだろうか?
最後に、研究や科学に対する非専門家のハードルを下げたいという意味がある。科学者のみならず、技術者、教育者、一般の人も科学技術のプレイヤーになって欲しいのだ。プレイヤーというのは何も第一線で研究をする研究者のことではない。宇宙の果てしなさに思いを馳せたり、生命の神秘に心が動かされたりするのならばそれは科学で遊ぶ人(player)といって差し支えないだろう。オランダの歴史家ホイジンガは著書『ホモ・ルーデンス』において、「人間文化は遊びのなかにおいて、遊びとして発生し、展開してきたのだ」と述べ、遊びが文化に先行すると述べた。科学が人間文化に包摂されるのだとすれば、科学もまた遊びとして発生し、展開していくのではないかと思うのである。
複雑化、高度知識化していく世界において、今後専門家と非専門家を繋ぐ必要性はどんどん増すだろう。AIの台頭やバイオテクノロジーの発展は、「命」とは何か「人」とは何かといった根本にある価値観を揺るがすからだ。これまで専門家の間だけで議論されていた研究内容や成果を実社会に接続するには、科学技術と人との新しい関係性とその可能性、リスクを提示し、議論を交わす必要があるのではないか。トランスサイエンスに対して、わからないと放置するのではなく、様々な問いを立てることが大切なのである。
科学とどう向き合い社会をどうしていくべきか、その答えを見つけるのは簡単ではないが、研究の未来をデザインするメディアLab-Onを通して未来への問題提起を行い、その答えのヒントを読者と共に模索していきたいと思う。
(脚注)
- 1999年10月26日に埼玉県桶川市のJR東日本高崎線桶川駅前で女子大生が元交際相手の男を中心とする犯人グループに殺害された事件。
- 非営利メディアについては、「NPOモデルのジャーナリズム – 米国調査報道の研究(独立メディア塾2014年11月号)」に詳しい。
- ラボはラボラトリーの略で研究室のこと。多くの大学の研究科には、分野やテーマごとに細分化された研究室と呼ばれる研究組織が置かれている。理系の学生の多くは学部4年次に特定の研究室に所属する。構成員は教授や准教授と学部、修士、博士課程の学生に加え、ポスドクや助教、秘書のいる研究室もある。各自のテーマに沿って実験や文献購読を日々行い、バイオ系では試薬の調整、消耗品の購入など研究室の維持に関わる活動にも取り組む。研究室に配属された学生は授業以外の時間の多くを研究室で過ごし、平日のみならず土日祝日も研究を行う研究室もある。